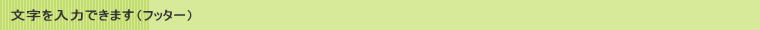☆1998年10月25日(日)
日曜日はお疲れさまでした。天気も良く、暖かくてラッキーでした。
来年の春に種をまいたり苗を植えたりする場所は今はまだ30年から40年生の杉の木が残っていて、これを切った後にまいたり植えたりすることになっています。切った木は、今の木材価格の状況から切り捨てにせざるをえないのですが、やっぱりもったいないなと思います。二酸化炭素の固定や治山治水、災害防止などのために、皆で木が大事だと言っている昨今、やっぱりおかしな話です。
山武地区の建築家の方々も、風倒木や切り捨てにされる木を見て、もっとその土地の木を建築に使えないかということでいろいろイベントをくんでくれていますが、肝心の生産者側の対応は今一つです。現状では、先方の求める価格では伐採、集材、搬出、製材すると赤字になってしまうからですが、自分も山に携わる人間としてなんかうまい知恵はないかなといつも思っています。
ただ、建築家の方々も言っているし、自分も確認したのですが、今建て売りで建てている住宅の建築資材の多くは爪をいれてみるときずがつく、やわらかい(植栽してから伐採するまであまり時間のたっていない・・・こういった木ははっきりいってあまりもたないです)木が多いですが、今回私たちが切ろうと思っている木の中には硬くて建築用の柱としてもっとずっともつような木がたくさんあります。
法隆寺の補修をしている大工さんは、「千年の木でつくった建物は千年もつ」というようなことを言っているそうですが、これから一生の買い物である住宅を補修しながら何年も使うようなライフスタイルになれば、こういった木が生かされるのではないかとも思っています。(そこまでいく前に何かほかの知恵を考えなければ間に合わないのですが・・・)
自分が広葉樹を植えようということで皆さんに声をかけているのも、お先真っ暗の林業の中でなにかいい知恵はないかなと模索している中でやっていることです。今後またいろいろとご協力お願いします。
今日の朝日新聞にもありましたが、生産者側からボランティアの方々を受け入れる場合、参加されるボランティアとのギャップが出る面があります。私自身も数年前にボランティアの方を受け入れようと思ったとき、危険な山作業でけがでもしたらどうしようかと思いました。でも、最近各地で山を手伝ってくれる方々を見ていると、レジャーとして山仕事をする人、育林に力を入れ山作業の技術的な面に深く関わっていきたいと考える人など、いろいろ考えがありますので、そうであれば、たとえば、「この山は、下にある人家に日がさすように、成長しても日照が確保される広葉樹を植えたい」という大まかな基本を提示して、あとは参加する人がどんなふうに関わってくれるか、お願いしてみようと思いました。そういう意味で、受け入れの面で試行錯誤しているのが実状です。
☆1999年2月7日(日)
今日は植林の準備の地拵え(伐採した木の幹や枝葉を片づける作業)を行いました。山作業の中でもけっこう大変な作業です。集合者は6人。
9:15頃現地到着、とりあえず、山の神の日だし、我が会としては初の本格的な作業日だったので、みんなで怪我のないことを祈って、清水さんが寄付してくれた日本酒で乾杯。場所は0.1haほどの北向きの中~緩斜面、伐採業者が切ってくれた37年生くらいのスギ(病気などで材木屋が引きとっていかなかったもの)が一面に倒れていた。
森林所有者でもある清水さんから作業手順の説明の後、作業開始。なれないチェーンソーや鉈をつかいながら、シロウトが持てる長さに幹を切り、枝葉をとってそれを一番下側に積み上げ始めた。10:30頃、休憩をかねて、平野さんの指導で鑑賞炭に挑戦。私が用意したマツボックリ、現地調達したスギ、ヒノキ、シダなどの葉を缶に入れ、たき火にくべる。
今日は快晴、風もゆるく、みんなけっこう汗ばんでいた。
再び作業開始。みんな頑張ったせいか、斜面の一部にスペースができたので、その部分を再来週に燃す(天気次第ですが)枝葉の集積場所とし、片づけを続けた。 午前中元気だったせいか昼までに面積の6割程度の片づけ終了、シロウト(清水さんは別ですが)でも人がいればけっこう進むものです。
昼飯を食べて鑑賞炭を取り出す。出来はマアマアでした。次回参加者は是非なにかあき缶を持ってきましょう。 午後はばててきたせいか能率が落ちました。
次回に片づける分もとってあるので、次回参加者は頑張ってください。
☆1999年2月21日(日)午前8時から
今日は残っている幹や枝葉の片づけとその火もし(焼却)を行った。
天気は快晴、本来火もしは雨の火にやるそうであるが、こういう活動ではやむを得ない。風がなかったので、予定どおり朝8時前から火もしを始めた。枝葉はすぐに燃えつきてしまうが、ちょっと太い木の幹が燃え切るまで時間がかかる。また、あまりいっぺんに燃すと火が上がり危ないので、現地に散らばっている枝葉を集め、火の様子をみながらくべていく。
参加者は23人、今日は人が多かったせいか11時過ぎにはほとんど片づけが終わった。
せっかく火もしをしたので、このなかの「おき」(火が十分まわり燃えている幹)を使い鑑賞炭を作った。続いて、昼近くなったのでやはり「おき」を使ってトン汁、スモークを行った。スモークは一斗缶を利用した簡単なもので、チーズ、ウィンナー、タコ、蒲鉾とそのままでも食べられるものを20~30分スモークし薫り付けをした。それと焼き芋。
午後は苗木や種をまいた位置の目印に使う竹支柱の先端削り。また切り株でも地上30cmくらい残っているものが何本かあったのでチェーンソーで切り直した。
順調に作業は進み3時頃終了した。しろうとでも大勢だとけっこう進むものである。これも人海戦術なんだろう。
☆1999年3月14日(日)午前9時から
今日は植栽や種まきの準備の支柱立てと掻き起こしを行った。
長い乾燥期が終わり菜種梅雨に入っていたので天気が心配だったが、朝起きたら太陽が出ていて一安心。スコップ、測量用のテープ(支柱の列をそろえるためのもの)などを用意して出発。
今日は19人が参加。最初に掻き起こしの場所を決め、それから支柱を立てていく列にテープや縄を張った。それから二手に分かれスコップで掻き起こしをするグループと支柱立てのグループに分かれ作業を進めた。掻き起こしは一部ササがあって、掘り取るのに苦労した。それでもこれだけの人数のせいか午前中に作業は終了。
昼にはスモークを実施。前回同様かまぼこ、ウィンナー、タコの他、今回はイワシの丸干し、ボイルしたホタテやツブ貝などにも挑戦。また休み時間に木登りや竹鉄砲づくりに挑戦する人たちもいて、いつものようにワイワイとやりながらの一日(半日)だった。
最後に、支柱の数を数え作業は終了。
みなさん御苦労様でした。
☆1999年4月4日(日)午前9時から
今日は苗木の植え付けと秋に拾ったドングリなどの種まき。
天気が心配だったが、予報でも雨は降らないらしい。先週までの雨で土は十分湿っており、風もなく、また快晴でもなく、苗木の植え付けには最高だ。
今日の参加者は23人、5つのグループに分かれて、用意したコナラ、クヌギなどの雑木苗木100数本を植えていく。続いて種まきとバウムクーヘンのための生地作りと火起こし。あっという間に昼になった。
午後はバウムクーヘンの生地を焼く一方、タケノコを探しに行く人、カタクリの花を見に行く人など様々にひとときを過ごした。
現地の樹種と本数(概数)
ケヤキ 苗22 種10 / コナラ 苗49 種50 / クヌギ 苗10 種20
ホオノキ 種15 / ヤマグリ 苗10 種15 / クマシデ 種10
コブシ 種15 / ムクロジ 種1 / イイギリ 種1 / ゴンズイ 種4
アオハダ 種7 / ヤマザクラ 苗11 / センダン 苗3 / エノキ 苗5
ムクノキ 苗10 / モチノキ 苗10 種6 / モミジ 苗2
☆1999年5月9日(日)午前10時から
今日は、4月に播いた種の発芽状況や苗木の活着状況をみて、種や苗木の位置にたてた支柱に、樹種の名前を書いたテープを貼り付けた。
山に播いたコナラの発芽はイマイチって感じだったが、発芽はマアマアだったし、苗木の活着は大変よかった。また、掻き起こしを試みているところはこれからなんだろう。
今回の参加者は20数人。初めての人もいたが、みんなけっこう山に慣れてきたようである。
昼時にはみんなで集めた山菜(タラノメ、ドクダミ、ユキノシタ、ニガキ、ミツバ、タケノコなど)を天ぷらにした。また、天ぷら用に起こした火の中にタケノコをくべて蒸し焼きにした。
天気も良く、ちょっと動くと汗ばむ。この先の下刈(草取り)はけっこう大変かも。でも人海戦術で頑張ろう。
☆1999年6月13日(日)午前10時から
梅雨時期、予定を組んだとき天気が心配だったが、梅雨とは思えない良い天気、これも異常気象なのだろうか。
今日は第1回目の下刈。ただし、現地は今年地拵えしたところなので、あまり草は伸びていない。
そこで、種を播いたところの間引きと草取りを中心に作業を行った。
発芽した稚樹の周囲20~30cm四方の草を抜き、また稚樹は3本くらいまで間引いた。
広葉樹の稚樹をみるのは始めての人が大多数、よく知っている人にああだこうだ聞きながら作業を進めた。
抜いた草は表土が流れないよう、また草の出を押さえるよう稚樹のまわりにまき散らした。
今日の参加者は、ニューフェイスもあり23人。これだけいると、こんな手の込んだ作業でもわずか1時間30分程度で完了。
しかも一人で黙々と行う山作業と違い、時間のたつのもあったいう間だった。
ちなみに掻き起こしエリアは、先週平田さんが間違えてきて、清水さんと終えてしまったそうで、今日の作業はなかった。
☆1999年8月1日(日)午前7時30分から
今年2回目の下刈。梅雨が明けた夏真っ盛りである。
炎天下の作業は避けて、朝7時30頃から始めた。
昨日から泊まり込みで来ていた人達もあり、8時ちょっと過ぎには21人が集まった。
半年前に地拵えしたばかりの場所とはいえ、梅雨時期の十分な雨のせいか、けっこう草は伸びていた。
下刈機や大カマも使ったが、掻き起こしゾーンや春に播種したところは、どうしても手作業になった。とはいえ、いつものとおりの人海戦 術でけっこう進み、10時30前に作業は完了した。
昼は皆でバーベキュー。これは夏の定番だけど、やはり暑い中でワイワイやるのはこれが一番かな!
ノドが潤い、お腹もいっぱいになった後、今後の計画を話し合った。
所有者の清水さんのほうでもう少し雑木林を広げる予定とのことであり、その部分をやらせてもらうことになった。
今年は、木の伐採や材の搬出までやらしてもらうことになった。 また、伐採した木を使って、ログハウスを建てたいという話が出たが、チェーンソーを使ったことがない人達がほとんどだし、これはおあずけとなった。
そのかわりでもないが、炭焼きや竈作りにも挑戦しようという話も出た。冬の作業も楽しみである。
☆1999年10月17日(日)午前10時から
去年に続き、今年も種拾いを行った。
今日(10月17日)は、やっと平年並みの気温、暑さに慣れてしまい、チョット寒い。
寒さのせいでもないだろうが、今日の参加者は9人-ちょっとさみしかった。
集合の後、山武町内の3ヶ所に分かれて種拾いを行う。コナラ、クヌギ、イヌシデ、エノキ、ムクノキ、エゴノキなど午前中で10数種類の種が集まった。
これだけの種類でどんな山ができるか楽しみである。これからも、このメーリングリストで山の作り方を相談していきたいと思った。
再度集合し、ドングリは殺虫、エノキなどは果肉(実の部分)を取り除き、それから数を数え、来春の播種用に保存しておく分と取り播き分に分けた。
最後に、畑に行って取り播きを行い3時頃に作業終了。
寒さでちょっと冷えた体に、清水さんの家でごちそうになった甘酒がとってもおいしかった。
☆1999年11月28日(日)午前9時から
無事に伐採作業を終了。
今日は、朝から太陽が顔を出し、11月下旬にしては寒くもなく作業日和といった感じであった。
この天気にも誘われたのか、集まった人数は大人と子供を合わせて30名あまり。遠く埼玉県から来た人もいた。
午前9時ころから集まりだし、まず、来月以降に予定している炭焼きのための材料にするため、落ちている杉の枝の葉を払い、一定の長さにそろえる作業を行った。
午前10時20分、いよいよ今日のメイン作業である杉の立木の切り倒し作業。専門家(2名)の実演の後、この人達の指導を受けながら、5名ほど(女性も1名が体験)がチェーンソーを使って木を切り倒す作業を体験した。みんな緊張していた。
まず、木を倒す側の木の根元付近に切込み(うけ)を入れ、その後、反対側を切り進みながら(おいくち)、別の一人(専門家)が切り口に先が尖った木を差込み、木を倒す方向へ押す。最後まで切ってしまうのではなく、少し残して、木が倒れ始めたらその部分を切り進むのがコツとか。でも素人には難しい。
切り進むのがうまくいかないと、別の方向に倒れてしまう。これが危険である。
高さ15メートル・35年くらいの杉の木が豪快に倒れていく。倒れるたびに地響きが起こる。
次に、倒した木の枝を払い、幹を3~4メートル位の長さに切った。これもチェーンソーを使ったが、この作業は女性や子供たちも体験した。
昼食時には、豚汁を食べながら、林業試験場の手嶋さんから、来月に行う炭焼き用のドラム缶釜の作り方や炭焼きの方法を伺った。
午後は、切った木をトラックに積み込む作業や炭焼きの材料造りやまきわりをした。
切り倒したばかりの木はまだ水分を十分含んでいて思った以上に重かった。
切った木(多くは専門家に切り倒してもらいましたが、全部で20本ぐらい切り倒し、切り倒した木1本から2~3本とれたので最低でも40本)は材木屋さんに売りました。さて、どのくらいの収入になったのか、後で報告します。
最後に、焼き芋を食べて、2時過ぎにけが人も出ることなく無事終了。
☆1999年12月19日(日)午前9時30分から
ことしも残り後わずか、そんな年の瀬も詰まった今日も約20人が集まった。
午前中は手島さんの指導のもとで、ドラム缶の炭窯づくり。
最初、清水氏宅の庭に集まり、グラインダーでドラム缶を加工したり、木酢液を取るための竹筒の用意をし、山に運んだ。
そこで前回作った炭用の材料(スギ)を入れ、設置完了。
竹筒の設置に多少手間取ったが、うまく作業分担をして、一応昼に完了。
午後は、平田氏による植物観察会。
作業している山とその周囲を2時間ほどかけて歩きながらいろいろな説明を受けた。
スギ林といえども、適度に明るければ、様々な植物があることがわかった。
シイ、ケヤキ、エノキ、ムクノキなどの稚樹も育っていた。
目を下に向ければ、それもまた楽しい世界なんだなあ。
☆2000年1月16日(日)午前9時から
今日は、今年始めての作業、炭焼き。
18人が集合。
炭窯の火燃し班、鑑賞炭用の材料収集班、来春播種する場所の目印用に使う竹切り班に分かれ作業開始。
10:20、煙突から出る煙の温度が80℃を越えた。炭窯内に着火したようだ。
鑑賞炭の材料も集まり、鑑賞炭づくりも始めた。そうこうしているうち、竹切り班が戻ってくる。作業は順調に進んでいるようだ。
12:30、シイタケ原木(コナラ)伐採班が出発する。残った人は竹の先端削りと火の番。
16:00、原木伐採班がトラックいっぱい(40~50本)の原木と一緒に戻ってくる。
煙突の煙も透明になってきた。炭焼きもそろそろ終わりか。
原木を降ろし、空気穴、煙突を塞ぎ作業終了。
今日は朝から日暮れまで、長い時間ご苦労様でした。
それにしても、昼にごちそうになった甘ミソのお餅?????はおいしかった(おやつのアンコロ餅??もうまかったけど)。
☆2000年2月6日(日)午前10時から
朝一で、前回焼いた炭窯を開けた。
出来が心配だったが、ほとんど未経験者ばかりの割には
けっこううまくできたようだ(ラッキー)。
そして、今日は地拵え。年間作業の中では一番の重労働だが、22人も集まった。やはりこの人数が集まると仕事が進む。
午前中2時間ほどでけっこう片づいた。
昼に恒例?の焼き芋、スモーク、そして竹を利用したパン焼き、カンをオープンに みたててピザ焼き、を行った。こういうものがあるとやはりビール・・・・。
しかし今日は作業中心なので、ホドホドにして、午後も片づけを続ける。
天気予報では下り坂であったがどうにか雨も降らず、大勢集まったおかげで午後2時過ぎに一応終了した。
☆2000年3月5日(日)午前8時から
昨日降った雨があがった(火燃しには雨の日の方がいいらしいが)早春の日、
朝早くから大勢集まり火燃し作業を始めた。今回も30人、大勢の参加であった。
火燃し作業が一段落してから、シイタケ、ナメコ、ヒラタケの植菌と仮伏せ作業、
前回地拵えした場所の測量(来月、種を播いたり、苗木を植える予定)を行った。けっこう時間がかかるかとも思ったが、いつもの人海戦術により午前中にあらかた進んだ。
午後は仮伏せの残り、昨春種を播いて芽が出なかった場所数の調査(48ヶ所あった)、そして火燃しで残った木の幹をトラックに積んで捨てに行く作業を行った。2時半過ぎにこれもすべて終了。最後に余興で作ったハムをみんなで食べた。心配していた火事、そして全員怪我もなくめでたし、めでたしのうちに、全日程を終了した。
☆2000年4月16日(日)午前9時から
昨日からの雨がちょうどあがり、植え付けや種播きには良いコンディションとなっ
た。いつもより早い9:00に集合(その前に苗畑からの掘り取り作業もあった)し、と
りあえず植え付け、種播き位置に竹杭を立てる作業に取りかかった。縄を縦横に張り、4尺5寸(135cm)に植え付けや種播きをした。途中で杭が足りなくなりあわてて 杭の調達というハプニングがあったせいか、昼の時点で種まきが残った。
しかし、昼は、予定どおり、めいめい持ち寄りのおかずで一杯・・・。ビール、日本酒、ワインがならび、タラノメ、ウド、モミジガサなど山菜の天ぷら、五平餅、ホ タテ焼き、焼き鳥、鶏の丸焼き、野菜や山菜の煮付け、酢の物など多彩な料理をつまみながら、いつの間にか時間が過ぎていった。
いつもより数倍長い?昼食の後、種播きをした。播いた種はカエデ、ムクロジ、ゴンズイ、クマシデ、コブシ、エノキ、ムクノキ、クリ、クヌギ、ホウノキ、ヤマコウバシ、エゴノキ、コナラの13種、水に冷やさなかったので発芽しない種があるかも 。
なんだかんだして3時過ぎに作業終了。今日も23人、大勢でやると種播きもあっという間だった(酔ってたからかも)。
☆2000年6月4日(日)午前10時から
ここのところいつも週末は天気が良くないので心配していたが、今日はとても良い天気だった。陽気のせいだろうか、いつもにも増して参加者が多く、今日は40人だった。
昨年より下刈面積(今年種を播いた分が増えた)は増えたが、いつもの人海戦術で午前中に終了した。作業開始後まもなく、アオダイショウが子ウサギを飲み込んでいるところを見つけて、皆しばし絶句のおまけつき。
午後は3月に植菌したシイタケ、ヒラタケ、ナメコの本伏せ作業を1時間ほど行い、最後に、現地から車で5分ほどの雑木林でヤマザクラの種を拾い終了。
☆2000年7月2日(日)午前10時から
7月2日の草取りは、前日からの蒸し暑く、厳しい暑さの中、10時頃からはじめた。
草は思ったより茂っていなかったが、人数は20人程度で、午前中には何とか終了できたが、あまりの暑さに30分も作業すると頭がボーっとなってくるので、木陰にしばしの休息を求めながらの作業となった。
現地で作ったアサリのスープを飲みながら、風が渡ってくる木陰で昼食を取って一息ついた後、午後は、現地を中心とした草花の植生を会員の平田さんの案内で1時間程度みんなで見て回った。
アー、暑かった。
☆2000年8月6日(日)午前9時から
去年も暑かったけど、今年はそれにも勝る猛暑!
そんな中で、今日集まったのは19人(数え間違えだったらゴメンなさい)。
作業は、モチロン下刈り、それとカマ研ぎ体験。
下刈機1台とカマ10丁ほどで作業を始める。
ここのところ雨も少ないせいか、草の伸びはそれほどでもない。
今年種を播いて、それほど伸びていないところを中心に作業を進める。
それでも作業開始から1時間たった10時を過ぎるとへばってきた。
11時に下刈り作業終了。
予定どおりバーベキューの準備にかかる。
暑さのせいか、売れ行きはイマイチだった。
1時からカマ研ぎを30分ほどやって今日の日程を終了した。
金親さん達は、今晩ここでキャンプする予定とのこと。
昼間は暑いけど、夕方から夜は涼しく、また星も見えるといいですね。
☆2000年9月10日(日)午前10時から
今日はみんなでソバ打ち作業に挑戦した。
ヤマの作業でなかったためではないだろうが,今回の参加者は20人ほどとやや少なかった。
会員の内山さんから丹誠込めて作ったソバ粉が提供され,ソバ作りが始まった。それと,付け合わせの天ぷら,ソバ粉を卵でつなぎ練ったものをバターで焼いた食べ物(一応ロティ-という)も作った。
作業を開始して3時間ほどたって,どうやら料理ができあがった。
みんなで打ったソバは平均4~5cmほどの長さだったが,味は見た目と異なり上々の評判だった。
飲み食いしながら今後やりたいことを話し合った。
所有者の清水さんから,もう少し隣接のスギ林を雑木林としたい(約5a)との希望があり,秋の種集め,冬の伐採,地拵え,春の種まきと補植(この春に畑に播いた種から作った苗木を利用),その他冬に竹炭焼きなどの日程が決まった。
また,スギ林を雑木林に変える場所は今回が最後となることから,今後の活動についてガヤガヤと話し合った。
その結果
1 清水さんの他のヤマを案内してもらいたい(現地を見る中で,今後会の活動の参考になる)。
2 今度伐採する場所の一部に小屋を作りたい。
3 今度伐採する場所の一部にブランコなどの遊具を作りたい。
4 実の成る木を何本か植えよう。
などが決まった。また参加できなかった人も勝手に意見を出してください)。
話が一段落した後,予定していた流しそうめんを無理矢理行った。最後に極め付きの流しジュース(みんなストローを口にくわえ,そうめんを流した竹を流れるジュースを飲む)をやって4時頃解散。
終わってみるといつもより長い作業???だった。
☆2000年10月1日(日)午前10時から
ここのところ、週末になると天気がぐずつついているが、案の定、今日もどんよりした朝だった。 しかも、天気予報もあまり良くなかったにもかかわらず、今日も20人が集まった。
午前中は、3回目の下刈作業、この春に播いた種から伸びたもののも、次々に草の中から顔を出し、来春の成長のための準備完了というところか。いさましく、初体験の草刈り機をまわすメンバーもいて、午前中に大部分が終わった。
午後は、現地で残りの下刈班と竹伐り班に分かれて作業を進めた。蚊と戦いながら炭焼きや来春の支柱用の竹を切り出し、なれないナタを使いながら竹割まで行った。
雨も降らずに、予定の作業を終了した。
今日は、子供たちが大活躍だった。
ごくろうさまでした。
☆2000年11月12日(日)午前10時から
昨日の好天と変わり、どんよりとした空。
天気予報の降水確率もやや高かった。
天気がどうあれ、種拾いを行わないと、来春の雑木山づくりができない。
午前10時。今回も28人集合。我会の会員達は日頃の行いが良いのだろうか。
雨の心配もほとんどなく、作業を開始した。
午前中、3班に分かれ、雑木林の近所の山に種探しに行った。前もって集めておいた分もあったため、集まった種の種類は18種類。
ヤマボウシ、コブシ、ヤマグリ、ケヤキ、クヌギ、エノキ、ムクロジ、ホオノキ、エゴノキ、ゴンズイ、ウワミズザクラ、コナラ、イロハモミジ、イヌシデ、クマシデ、ヤマザクラ、ヤマコウバシ、カマツカ。
昼食をはさんで、果肉を除去したり、翼をとったり、種子の精選作業を行った。
精選した種子の3分の2は来春の播種用として、砂と混ぜて再び冷蔵庫へ。
残りは清水さんの畑に播いた。結局終わってみると3時30分過ぎだった。
☆2000年12月3日(日)午前10時から
今日は、20世紀最後の活動日、20人が午前10時に集合した。
ドラム缶を掘り出し、材料の竹の節取り、そしてドラム缶への竹詰めを始めた。
1時間ほどでかなり進んだので、支柱用の竹の運搬班、芋煮鍋作成班、炭焼き準備班に分かれた。竹の運搬班は、けっこう急な斜面からの竹の担ぎ出し作業
だったようだ。竹を現地まで運んだ後、ノコギリによる竹の切断、ナタでの先削り、最後に並べるまでを流れ作業でこなす。
ちょうど終わった頃、芋煮鍋もでき、初参加の土屋さん差し入れの
濁り酒などもふるまわれ、 忘年会?を兼ねて昼食。
午後は、片づけなど1時間ほど軽く作業をして、今日はおしまい。
皆さん良いお年を!
☆2001年1月13日(土)午前8時から
年間作業の中で一番大変な地拵えを行った。
炭焼きも兼ねていたので、冬にも関わらず、集合は8時と早かったが、
30人ほどの仲間が集まった。
作業地は伐採したスギの幹や枝葉に覆われ、歩くのもちょっと大変な感じでもあった。炭窯に火を入れ、続いて幹や枝葉の片づけを始めた。
小屋作り用に幹を4mに玉切って積み上げるもの、枝葉を下部のスペース
や脇のスギ林内に運ぶものなど、大勢にも関わらず、順調に作業は進んだ。昼頃にはかなり片づき、地表面が見えるようになってきた。
昼食後は、火燃し用の枝葉の山を作るなどして2時頃に作業はほぼ終了した。
平行して作っていたハムもできあがり、いかのスモーク、きりたんぽなども登場して、ちょっとした新年会?を行い日程を終了した。
炭焼きは最初順調だったが、一度火が消えかかるなど、今回はちょっと?。
次回、竹炭の取り出しだが、結果はどうだろうか。
☆2001年2月25日(日)午前8時から
今日(25日)は火燃しの日。
前日の雨も上がり、晴れ間が広がり、またそれほど寒くもない。
現地に隣接している畑からは水蒸気が立ち上っていた。
作業は8時からで、私が遅れて着いたのが9時過ぎだったが、すでに35人あまりが集まり、枝葉を集めて燃やしたり、前回に引き続き、伐採した杉の幹を4mに玉切って積み上げたり、皆忙しく活動していた。
また、鑑賞炭つくりや昨年失敗した土器焼きに再度挑戦した。
作業は順調に進み、昼頃までには、火燃しや玉切りもほとんど終了した。
火燃しで、皆、顔が火(日)焼けしていた。
豚汁付きの昼食後、玉切ったものの皮むきと炭出し。
前回火が消えかかって心配した炭焼きでしたが、開けてみると竹炭はきれいにできあがっていて一安心。
また、土器焼きも前回の教訓が生かされ、今回はほとんどうまくいった。
そして3時前には予定していた作業はほぼ終了。
参加者の皆さん、ごくろうさまでした。
次回は3月18日(日)。
玉切った120本あまり、今後はしばらく皮むき作業が続きそう。
ログハウスの完成を願い、皆さんがんばりましょう。
☆2001年3月18日(日)午前10時から
予報では天気が回復とのことであったが、昨日からの雨がなかなかやまない。これで雨があがれば、種播き、植栽には最高だなあと思っていると、10時30分すぎにどうやら雨もあがった。
20人の参加者が、種播き、植栽位置への竹杭立て、バウムクーヘンの準備を始める。開始が遅れたこともあり、竹杭立てが終わったところで、午前中終了。平田さんがお酒を差し入れてくれたので、杭の余りで急きょコップを作る。
午後は今年伐採した斜面の下の方の苗木植栽とバウムクーヘン作りから始めた。植栽が終わった頃にバウムクーヘンもできて、一休み。最後に種まきと昨年播いて芽が出なかったところに苗木を植栽して、日程を終了。
気がつくと4時、日が長くなったものである。
☆2001年4月15日(日)午前10時から
今日は初夏を思わせるような陽気でした。
そのためか?、30人も集まった。
午前中は、自然観察+野草収集班、たけのこ収集班、皮むき班に分かれて
作業を実施。
ちょっと遅めに野草の天ぷらで昼食。陽気のせいか、ビールの売れいきが上々だった模様。
2時頃から1時間30分ほど全員で皮むきをした。
そんなわけで、今日の作業を終了した。
ところで、今日皮をむいた丸太の本数を覚えている人がいたら、投稿してください。
追伸:皮を剥いた丸太の本数は20本(うち1本は途中)だそうです。
残り約100本。
☆2001年5月20日(日)午前10時から
今日も初夏を思わせるような日差しが朝から出て、皮むきにはちょっと不向きかなと思いつつ、現地に向かった。
今日の参加者は8人(大人7人、子ども1人)。
急に日程を追加したため、参加者は少ないだろうとあきらめていたが、やっぱり予想どおり。
現地は草もかなり生えてきていて、次回(6月17日)の下草刈は大変だろうなあと思いつつ見て廻ると、何本かの木(コナラ)に何十という毛虫がまとわりついて、音を立てながら葉を食べていた。
議論のあるところだとは思いながら、このままでは葉をすべて食べ尽くされて枯れてしまうと思い、毛虫を駆除(焼却)することに。
その後、日陰を選んで、今日のメインメニューの皮むきに励んだ。
途中、昼食時にはビールで十分水分を補給して、午後3時までで、12本の皮をむいた。
今日は、江戸川大学の学生さんが初参加で、彼は、富山県の草刈十字軍に参加されているそうで、その話を聞き、他の参加者も思わずがんばってしまいました。
これで、トータル38本の皮むきが終わったことに。でも、まだ70本ほど残っています。まあ気長にやりましょう。
☆2001年6月17日(日)午前10時から
昨日までの雨があがった。どういうわけかこの会の活動日は雨にたたられることがほとんどない。
今日は、ムシムシする中での下刈りと皮むきもかかわらず34人と大勢が集まった。
午前中は下刈り、下刈り機も3台フル稼働して、あっという間に終わり、11時過ぎには早くも皮むき作業が始まった。
昼休みはカンを簡易オープンに仕立ててピザを焼いた。煎餅などの入っていたカンと炭、コンロのようなものがあればできるので、これはお手軽である。
午後は何カ所にも別れて皮むきを続ける。2時過ぎには約20本の皮むきが終了した。
☆2001年7月8日(日)午前10時から
今日は前回とうってかわり、参加者は7人だった。しかし、梅雨にもかかわらず雨が少ないせいか草はあまり伸びていない。
そんな状況だったので、ひとしきり今後の山づくりなどを話し合い、その後必要なところを下刈りを行い、昼を食べて今日の作業を終了した。
☆2001年8月5日(日)午前9時から
今日は夏休み真っ盛りで皆さん家族旅行等に出かけたのか9時過ぎに集まったのは大人8人、子ども3人の計11人と少数でした。
今回は前日(4日)の夜に8人(大人5人、子ども3人)が集まって、現地でアルコールなどを飲みながら、山づくりのことやログハウスのことなど(?アルコールが進み、かなり脱線したようですが、よく覚えていません。)を深夜まで語り合いました。
このうち、4人は現地にテントを張ってキャンプをしたのです。
この夜は暑くもなく、逆に夜が更けるにしたがって、半そででは少し寒いくらいの気候で、お酒も話も弾みました。
さて、今日の作業の話に戻りますが、前日の段階で参加者が少なそうだということで、清水さんが草刈機で半分ほど刈ってくれていたので、参加者は今年植えた場所の下半分を中心に草刈を行いました。
幸い午前中は曇り空で、あまり暑くもなく、去年のように日陰に非難するということもなく、草刈も順調に進み、人数が少ない割には、11時過ぎには予定の場所を終了しました。
その後日陰に移動し、バーベキューをしながら、今後のことなどを話し合いました。
参加者の中に、木工や設計の仕事をされている人がいることがわかって、今後のログハウス作りに明るさが見えてきました。
今後の日程(9月16日、10月14日)を決めて14時過ぎには解散となりまし
た。
☆2001年9月16日(日)午前10時から
今朝はこの会の活動が始まって始めてというくらいの大雨だった。
そこで、日程を変更し、午前中にウィンナー作りをやった。
参加者は17人、みなさん興味しんしんで、経験者の西野さんの説明をメモ書きするくらい熱心に聞いている人もいた。
昼にはほぼ雨もあがり、できあがったウィンナーを食べ、流し素麺も行った。
午後は2時間弱、草取り作業、毎度のことですが、みるみるキレイになっていった。
3時過ぎに作業終了。ご苦労様でした。
☆2001年10月14日(日)午前10時から
秋晴れの中、今日の参加者は19人だった。
作業は丸太の皮むき、また昼には、ハタケシメジやサクラシメジの入ったきのこ汁、焼いも、ゆで落花生を作った。
そのおかげで、みんな頑張ったせいか、今日は34本とはかどった。皮むき作業も先が見えてきたようです。
☆2001年11月11日(日)午前10時から
今朝はこの秋一番の冷え込みだったけど、晴天に恵まれ、作業を始めるころは暖かくなってきた。
参加者は20人、その他校内にビオトープ作りに使う丸太を引き取りにを扇田小学校の先生が4人きた。午前中、丸太の積み込み、皮むき(20数本)を行った。
100余本の丸太すべての皮むきが終了した。みなさんご苦労様でした。
また、来春補植のため、種を蒔いてうまく育たなかった箇所の調査も行った。110ヶ所ほどあり竹杭に黄色いテープを巻いた。播種したものが育ってきたため、すべての箇所に補植が必要ではないかもしれないが、部分的には育っていないところもあるようである。
昼にきのこ汁とスモークを行いながら、いよいよログハウス作りの話し合いをした。先月、神奈川県自然環境保全センター研究部の中川重年氏に聞きに行ったこと、丸太の組み立て方などの話が金親さんからあり、いよいよログハウス作りが具体化しつつあると思った。
この他、雑木林についてのこれからの仕立て方などの話題も出て、我が会の活動に新たな展開が始まるような予感がした。
☆2001年12月16日(日)午前10時から
昨日の強風も収まり、雲ひとつない晴天に恵まれた。が、やはり12月、日陰に入るとかなり寒い。
それでも今日は初めての人も含めて20数名集まった。
まずは、皮むきの終わったログハウス用の杉材を柱用、壁用に分けて積み替える作業を行った。伐採して数ヶ月たっているというのに伐木はまだ重かった。
しかし、人数も多かったせいもあり、休憩を入れながらも昼前には作業は終了した。
昼は、皆が持ち寄った野菜、肉、さらには現地でできたたくさんのシイタケを入れた鍋料理、秋刀魚の塩焼き等を肴に、ビール、日本酒、ワインで、さながら忘年会となった。皆、大いに盛り上がった。
午後は、来月の炭焼きの準備。
伐採してあったサワラの木を85センチメートルの長さにチェーンソーで玉切って、斧で薪割り。面白いように簡単に割れるので、皆、けっこう楽しそうだった。そして、それをドラム缶釜一杯に詰め込んで、土を被せて準備完了。
15時過ぎには今日予定の作業はすべて終了した。
皆さんご苦労様でした。
☆2002年1月20日(日)午前10時から
今回のメインは炭焼き、9時過ぎに窯に火を入れる。
9時半過ぎから若いスギ林で枝打ちを行う。清水さんから説明の後、四苦八苦しながら枝を落とした。
約2時間かけて30数本の枝打ちを完了した。わずかではあるが、暗かった林が多少は明るくなったようである。
今回は、炭焼きの体験をしたいという千葉市立扇田小学校の生徒、父兄、先生、インターネットで知った初参加者数名が加わり、総勢なんと41人だった。
炭焼きは、着火後にいったん温度が下がってしまい、再度燃やしたため、5時頃までかかった。窯をふさいで片付けたら5時半頃、遅くまでお疲れ様でした。
☆2002年2月10日(日)午前9時から
今日からログハウス作りに着手した。
最初に金親さんから概要を説明してもらった後、丸太の径を計る班と柱の溝掘りなどの練習をする班に分かれて作業を開始した。
同時に前回の焼いた炭を取り出した。ちょっと炭になってないものもあったが肥料袋半分ちょっとの収穫だった。次回また炭焼きするため、引き続きその準備を行った。
ログハウスの方は、練習のかいあって??チェーンソー、かんな、のみ、鋸などを使って、どうにか作業が進められそうな気がしてきた。
午後には雪がチラチラする寒い日だったか25人の参加者があり、怪我もなく一日終わった。
☆2002年3月10日(日)午前9時から
今年は春が早いようで、この日も暖かな一日だった。
作業は、炭焼きとログハウス作り、参加者は24人だった。
炭焼きは前回、暗くなるまでかかったので今回は早めに火を入れた。今回は順調で10時すぎには窯に着火した。
ログハウス作りは、皮をむいた丸太のうち、柱、土台、梁に使うものを所定の長さに切り、製材所でタイコ挽きをしてもらった。その間に、基礎に使う枕木の準備などを行った。今回は丸太の積み卸しや移動など結構体力を使う作業もあり、皆さんご苦労様でした。
☆2002年4月14日(日)午前10時から
ログハウス作りも徐々に軌道に乗りそうですが、今後、それなりにお金がかかるようです。その資金をどうやって調達するかなど、まだまだ問題はあるようです。
今回のメインは雑木林の補植。
20数名が集まったポカポカ陽気の中、清水さんの畑で育てていた苗木の掘り取りから作業が始まった。
コナラ、クヌギなどの苗木をめいめい芽が出なかった場所に植えていった。
みんな作業になれてきたこともあり?、午前中で完了した。
昼は、春恒例の山野草の天ぷら。タラノメ、タケノコなどのほか、アオキの葉やツバキの花などまで盛りだくさんだった。
午後はログハウス作り、試行錯誤しながら間柱に利用する12本の加工、気がつくと16時近かった。
追伸
前回焼いたサワラの炭は、結構良い出来だった。
☆2002年5月12日(日)午前10時から
ここのところ天気が悪く、今日もどうかと思ったが、久しぶりに雨を心配しなくてすんだ。しかも、あまり暑くもなく作業日としては適当だった。
今日の参加者は15名、いつもに比べるとちょっと少なめだった。
最初の作業は草刈り、例年よりも暖かいせいか、けっこう下草が伸びていた。去年種まきしたエリアを中心に手刈りで行った。その中にキジが巣を作っていた。刈り払い時点で気づかなかったため親鳥は逃げてしまったが戻ってくるだろうか。また、前回補植した苗木はけっこう葉が枯れていた。ゴールデンウィークまで乾燥気味だったせいだろうか。幹はまだ生きているので復活することを期待しよう。
午後は、ログハウス作り。土台と隅の柱の加工を行った。作業としてはあまり進まなかったが、慣れてきたので次回はけっこう進むのではないだろうか。
なお、今日は「シティライフ」という地域情報紙の大谷さんという記者が取材に来た。我々の勇姿が?紹介されるようである。
☆2002年6月9日(日)午前10時から
盛夏を思わせるような晴天の一日、下刈り、そしてログハウス(一説では掘っ建て小屋)作りを行った。参加者は10人と少なかったが精鋭部隊?ちゃくちゃくと下草が刈られていく。炎天下にもかかわらず午前中にあらかたの草を刈り取る。
昼は一斗缶の釜戸を使ってパン焼きに挑戦。この他、11月に行われるエコメッセへの参加やログハウス作りのための資金の調達方法などを話し合う。
午後は残りの草刈り、そしてログ材料の柱や土台の溝切り。
そして、最後に食べた隣の畑のおじさんからいただいたスイカがとてもおいしかった。ごちそうさまでした。
☆2002年7月21日(日)午前10時から
梅雨が明け、毎日、ほんとうに暑いですね。
そんな一日でしたが、36人の参加の中、午前中下刈りを行った。
一時間半程度で作業は終了したものの、かなりハードだった。
昼には、一斗缶を使って豚肉の塩竃を作った。塩の残った?ところはしょっぱかったがまあまあの出来。ただし、こんな陽気で火を焚いたのはしんどかった。
昼食をとりながら、前回に引き続きエコメッセ参加についての相談をした。様々な意見が出たが、一応参加の方向にまとまった。
午後は、ログハウス作りや夏休みの宿題?用の葉っぱ集めなど、各々活動を行って3時30分頃終了。
皆さんご苦労様。
☆2002年8月11日(日)午前10時から
今回も下刈り作業、梅雨明け後の猛暑、晴天続きだったのに、思ったより草が伸びていた。
参加者は二十数人、さすが慣れてきて、手鎌、下刈り機などを使って、
めいめい作業に取りかかる。いつものように午前中でほぼ終了。
昼は、夏恒例のバーベキュー、猛暑の今年は、森の中に避難して行う。
羊の骨付き肉や焼く鳥まであって豪華メニューだった。
十分な休息をとった後、また山に入ってつる切りなどの作業、ログハウス作りなどを行った。
エコメッセについては、活動内容等の展示の他、丸太切り、コースター作り、筆立て作りなどを行うこととなった。
この他、11月9、10日に山武町で行われる「全国森林環境シンポジウム」への参加要請が主催者からあり、お手伝いすることとなった。
☆2002年10月13日(日)午前10時から
秋晴れの一日、11月のエコメッセの準備を行った。
参加者は8人と少なかったが、少数精鋭???。
午前中は展示パネル用の準備、午後は木工(筆立て、コースター)
および丸太切り体験用の材料集を集めた。
また、先日の台風で、隣接のスギ林で折れたスギ数本を片づけた。
このほか、エコメッセ準備の打ち合わせの中、当日豚汁を作り、
運営資金の一部にすることとなった。
エコメッセ当日はそれなりに人手がいるので、
みなさんふるって参加しましょう。
☆2002年11月10日(日)午前10時から
寒さが心配でしたが、昨日とはうって変わって、風もなく、良い天気になりました。
昨日、今日と山武で森林環境教育シンポジウムが開かれており、そちらに行った人もいて、10時に集まったのは8名といつもより少なかった。
(その後人数が増えて、午後には20名ほどに。)
早速、下刈りとログハウスの柱に使う木の溝堀に分かれて作業開始。
下刈りは、最初に植付を行った場所を中心に行った。
下のほうは、かなり笹が生い茂っており、草刈機でも結構大変でした。
昼食をとり、午後は溝堀が中心。
子供たちも上手にノミとカナヅチを使って溝を掘っていきました。
初冬の日差しは、結構暖かく、また眩しかった。
午後3時過ぎには終了。
次回は12月8日(日)10時からで、ログハウスづくりと、材料が間に合えば、炭焼きをすることにしました。
炭焼きをする場合は8時ごろから火をつけます。
また、今年最後の活動なので、参加者各自が1品持ち寄りで、昼食時に忘年会をすることにしました。
日ごろなかなか参加できない人もぜひ参加してください。
また、エコメッセちば2002と森林環境教育シンポジウムに参加しました。
☆2003年1月19日(日)午前10時から
新年おめでとうございます。遠藤です。
朝も雨が落ちるなどあいにくの天気だった。参加者は15人。
炭焼きの予定だったが、材料を用意して、ドラム缶の窯につめ、たき口を作り、最後に窯に土をかぶせるなど準備が終わるともう昼だった。
いつものように、みんなでのんびりお昼を食べていると、雨が降ってきた。
空も暗いし、寒いしで、午後の作業は中止となった。
炭焼きは次回(2月16日-第三日曜日)となった。
また、3月は第二日曜日を作業日に決めたので、みなさん予定にいれておいてください。
☆2003年3月9日(日)午前9時から
ここのところ、当会の活動も雨にたたれて
なかなか思うような作業ができませんでしたが、今日は久しぶりに天気に恵まれました。
朝、9時前にはドラム缶の炭窯に火を入れ始めました。
10時過ぎに集まったのは9人。
杉花粉症や風邪で参加者が思っていたより少なかった。
炭焼きは、気温が低く、ドラム缶を覆った土に霜柱が
立っていたので、中に着火したのは10時30分を過ぎていた。
一方、このところの雨と気候で、シイタケが大豊作。
スーパーの大きなレジ袋3袋分はあった。
昼には、この肉厚のシイタケを焚き火で焼き、醤油とマーガリンを付けて食べ、残りはお土産に。
(500円の参加費のもとは十分すぎるほどとれました。)
午後からは、ログハウス用の材の溝堀。
人数が少なかった割には結構はかどりました。
今後の予定を決めて、16時過ぎには解散。
なお、炭窯は17時30分過ぎには火を消しました。
参加された方にはお疲れ様でした。
今後の予定はつぎのとおりです。
4月13日(日)午前10時から炭出しと溝堀、昼は山菜のてんぷら。
5月はお休み。
6月8日(日)午前10時からログハウス用の穴掘りと土台づくり、下草刈。
7月26日(土)~27日(日)ログハウス棟上げ、下草刈。
☆2003年4月13日(日)午前10時から
昨日の雨も上がり、10時過ぎには20数人が集まった。
まず、先月の活動で焼いた竹炭をドラム缶窯から取り出した。
入り口付近は、灰になってしまっており、また、奥のほうは
下部が十分炭になっていなかった。
原因はドラム缶設置の際、前方が低くなってしまい、水平に設置できなかったことか?
次に、昼食時のてんぷら用にみんなで付近に山菜採りに出かけた。
タラの芽、三つ葉、ゼンマイ、どくだみの葉など数種類を集めた。
また、タンポポの花、栽培していたしいたけを採り、先ほど採ってきた山菜とともにてんぷらにして食べた。
午後は、ログハウスの柱用材の溝掘り。
チェーンソー、ノミを使い、人数が多かったせいもあり、柱用材の溝掘りは16時過ぎにはすべて無事終了した。
今日は思ったほど晴れなかったが風もなく少し暑い日でした。
参加された皆さんお疲れ様でした。
5月はお休み。
6月は、8日(日)午前10時から
ログハウス用の穴掘りと土台づくり、そして下草刈を行います。
みなさん、予定に入れておいてください。
☆2003年6月8日(日)午前10時から
今日はおよそ2か月ぶりの活動でした。
朝、現地に行ってみると、予想はしていたけれど、下草が生い茂り、人出がいないと大変だなあと感じた。
10時に集まったのは3人。
曇ってはいたが、予報では晴れてくると言っていたし、気温は上がるだろうし、どうなることやら。
早速、草刈機2台とカマで下草刈開始。
徐々に人数が増えたが、子供たちが運動会やらで最終的な参加者は大人が9人。
昨年、一昨年に植えたところを中心に下草を刈った。
昼前に、埼玉県の都幾川村の「どんぐり山を守る会」の人たち30人ほどが見学に見え、昼食を食べながら談笑した。
(私たちの活動が役に立つのだろうか。と思ったりもした。)
また、昼には、会員の一人が持ってきてくれたイノシシとシカの肉を焼いて食べた。
なかなかの美味でした。
午後、下草刈りとログハウスの土台用の穴掘り準備に分かれて活動再開。
下草刈り班は1時間弱ほど作業をして(日焼けして)、ログハウス班に合流した。
土台用の穴掘り(4か所)をして、2か所に土台用枕木を入れたが、その後、4か所を結んでの直角が取れなくてそれ以降の作業は来月に延期することにした。
終わったのは17時。皆さんお疲れ様でした。
参加できなかった皆さんへ
7月の日程が変更になりました。
7月26、27日だったのが、7月20日(日)、21日(月)に変更になりました。
下草刈りとログハウスづくりです。1日のみ参加でも構いません。
また、8月は10日(日)になりました。これから暑くなりますががんばりましょう。
☆2003年7月20日(日)、21日(月)午前10時から
今年は梅雨明けが遅く、小雨が時折落ちる二日間であった。
20日、13人が集まり、午前中は雑木林の下刈を行う。
作業を行いながら、「けっこう大きくなったね」、「そろそろ下枝を払っても良いかな」などという意見が出た。
昼は夏恒例のバーベキューをして、またいつものとおりゆっくり体を休め、午後はログハウス作り。基礎に使う枕木を四隅に設置した。4ヶ所の高さを揃えたり、直角を出すのに苦労したが、どうやら完成。前の週にもトライした一部会員の努力もあり、
見事な?出来映えだった。
21日、15人が集まり、ログハウス造りの続き、前日設置した枕木の上に土台に使う横木を乗せたり、ちょっと柱を立てたりして、様子を見る。
なんとなく、作業が進んでいることを実感できた。柱と土台の接合部の微調整を行ったり、今後の作業の段取りを相談して、あっという間に二日目も終わった。
☆2003年8月10日(日)午前10時から
台風一過の猛暑の中、13人が集まった。
前回から三週間ほどで、草はあまり伸びていなかったので、
ログ作業の場所などの草を少し刈った後、梁材にほぞあけ作業を行った。
電動ドリルが威力を発揮し、梁材2本分だったがかなり進んだ。
11月の上棟をめざし、何とか頑張りましょう。
☆2003年9月14日(日)午前10時から
今年は9月に入って真夏の暑さが続いてますが、今日も暑い一日だった。
参加者は精鋭?12名。この暑さと8月の雨のせいか、けっこう草が伸びていた。
今日の作業は草刈りとログハウス作り、ログハウスは、前回に続き、まず梁材のホゾ穴空けを行った。その後、角の柱を立てて土台材とのかみ合わせをチェックした。
予定どおり11月に棟上げするためには、
1.長い2本の梁材を一部切る
2.短い2本の梁材に間柱とのかみ合わせのホゾ穴空け4箇所(2箇所×2本)
3.梁材どおしをかみ合わせるカット作業8箇所(1本につき両端の2箇所)
4.間柱を建てて土台材とのかみ合わせをチェック
5.基礎の枕木の埋め込み4箇所(4方向1箇所ずつ)
が必要である。
この作業は一日では無理そうであり、次回は11(土)と13(月)に作業を行うこととした。
ヤマグリの実が落ち始めていた。みんなで拾ったり、実を叩き落としたり、
40~50粒が集まった。今晩栗ご飯の人もいたかな?
☆2003年10月11日(土)、13日(月)午前10時から
今回はログハウス棟上げのための最後の準備でした。
三連休のため、参加者は8人と少なかった。
短い方の梁に間柱用のホゾ穴を開け、長い梁との重ね合わせの
部分の切れ込みを行った。
また、相談の結果、梁材の持ち上げは三脚櫓を建ててチェーンブロック
で引き上げることとなった。
いよいよ来月の作業日に雨が降らないように祈るだけである。
☆2003年11月15日(土)午前9時から
いよいよログハウスの棟上げの日。
(屋根の部分はまだですが。)
15時ごろから雨が降り出すという天気予報で少し心配はあったが、9時ごろから参加者が集まり出し、強力な助っ人も含めて18名が参加した。
まず、四隅の柱をボルトで土台に固定し、間柱を立て、
上部の梁を三脚櫓を建ててチェーンブロックで引き上げ、
最後は梯子に登った人たちがそれをさらに持ち上げ、
柱のほぞをほぞ穴にはめ、鎹を打ち込み、
さらに羽子板ボルトで梁と四隅の柱を固定する。という作業を繰り返した。
途中、ほぞがほぞ穴に入らないところもあったが、
削ったり、たたいたりして、修正しながら、
また昼食の時間を十分とったのに、15時ごろには予定の作業を終了した。
事前の予想ではもっと時間がかかると思われたが、
強力な助っ人と皆の協力のおかげで無事棟上げすることができました。
本当にありがとうございました。
その後、残った人たちで、屋根の構造や今後の日程などを打合せをしていたら、どしゃ降りの雨に。
作業中でなくてほんとよかった。
皆さんご苦労さまでした。
なお、今日の作業の様子を佐倉のケーブルテレビが取材していきました。
☆2003年12月14日(日)午前10時から
前回は棟上げで大変だったせいか、今回は7人と少なかった。
午前中は、結局、金親さんが持ってきてくれたつくねや藤村さんが
持ってきてくれたサツマイモをやきながら屋根作りの話しをして過ごした。
その他清水さんから、この冬に雑木林の一部で、間伐や枝払いが必要
と話しがあった。
午後は、柿渋塗り、束木の加工、梁に束木を入れる穴空けなどをおこなった。
穏やかな一日だったが、3時をまわると冷えてきた。
☆2004年1月24日(土)午前10時から
今回の参加者は9名だった。
ログハウス屋根作業のための支柱と棟木?を引き取りに出かけた。
また、中央博の林さんの講座参加者がみえたので、会の活動、
山武のスギのことなどの説明、近くの大スギの案内を清水さんが行った。
最後に、次回の作業について相談し、ログハウス作りと雑木林の枝払い
を行うことになった。
☆2004年2月8日(日)午前10時から
今日、現地に集まったのは清水さんと私のたった二人、、、、、、、、、
ということで、作業は行いませんでした。
雑木林を少し見て、枝払いの他、成長の良すぎるセンダンはすこし幹止めをしたり、
下部から二股になっているものなどは整理したらなどと話しました。
根性もなくて、今日は山の手入れをしなかったので、是非とも次回は
頑張りましょう。みなさん大勢来て下さい。
☆2004年3月14日(日)午前10時から
今日の参加者は8人。
船橋市から桑原さんが初参加でした。
午前中は広葉樹のすそ払い、一部しかできませんでしたが、
行ったところはけっこう見通しが良くなりました。
午後は足場作り、けっっこう時間がかかるかと思いましたが、
分担して作業した結果、スムーズに完成しました。
これと並行して、梁材へのホゾ穴明けも70%くらい進みました。
11月に棟上げしてからあまり進みませんでしたが、
このペースで進めば、今年中に屋根ができるかもしれません。
☆2004年4月11日(日)午前10時から
天気もよく、久しぶりに子どもたちの参加もあり、総勢18名で賑わっていました。
作業のスタートは、ログハウスづくりの場所の草取り。
作業がしやすいようにみんなで周辺の草を鎌や素手で取り除きました。
それから、梁材へのホゾ穴あけや、ログハウスの柱に柿渋を塗ったり、
足場用の板に(足場は1年くらい使いそうなので)防腐剤を塗ったりしました。
昼は、栽培していたきのこや現地にあったタラの芽、タンポポの花や野草を
天ぷらにしたり、参加者が持ち寄った食材を炭火で焼いたりして食べました。
午後は、足場用の板の取り付け、杉丸太を切断し、
鋸で加工して壁材づくりなどをみんなで手分けして行いました。
壁材がうまく溝に入らなくて苦労しました。
四方に窓を付けようと話して16時ごろに終了しました。
5月はお休みで、次回は6月13日(日)です。
☆2004年7月11日(日)午前10時から
午前中は下刈り、午後はログハウス作りを行った。
今年は7月に入り雨が少ないため、草の伸びはそんなに多くはなかったが、
むっとするような暑さの中、重労働だった。清水さんが差し入れてくれたすいかが、
ナント美味しかったことか。
午後のログハウス作りでは、棟木があがり、壁も何段か積み上がった。
やっと目に見えて進み始めたようである。
最後に、また清水さんから茄子とトマトをお土産にもらい、心身とも?充実した一日だった。
☆2004年8月8日(日)午前10時から
猛暑の中、参加者は11人。
雨は降らなくても草は伸びるようで、いつものように午前中は草刈り。
熱中症にならないようにゆっくり休んだ?後、ログハウス作り。
壁材の落とし込み作業と屋根の垂木及びコンパネの設置方法の検討を行った。
次は頑張って垂木設置、コンパネ及び防水シート張りをやろうということになった。
☆2004年9月19日(日)午前10時から
参加者は20人を超えていた。
午前中は草刈りとログハウスの屋根の垂木設置。
子どもたちは現地にできた栗拾い
昼食後、壁材の落とし込み作業と
安全に配慮しながら、屋根にコンパネ及び防水シートを貼った。
次回は、杉皮を屋根に貼ることにした。
☆2004年10月11日(月)午前10時から
台風22号の影響で防水シートがすべてはがれてしまった。
雨で危険なので作業はせずに
集まった人たちで今後の相談をした。
防水シートのままだと、また二の舞になる恐れがあるので
次回は2日間続けて作業をし、防水シート貼りと
杉皮貼りまで終わらせてしまうことにした。
今回は屋根作りを行いました。
台風で防水シートが飛ばされたため、今回は防水シート張りと
屋根材(スギ皮)張りを一度に行いました。
1.台風で少し傾いた柱の手直し
2.火打ち金物の設置
3.足場の改良
4.防水シート張り
5.スギ皮張り
6.スギ皮を押さえる角材設置
7.仮筋交いの設置
内容が盛りだくさんだったうえ、ちょっとトラブルもあったりしましたが、
好天に恵まれ無事終了しました。完成にはまだまだですが、遠目からも
屋根ができてちょっとかっこいいかも(自画自賛)。
参加者は20日6人、21日5人、少数精鋭?
参加者の皆さんご苦労様でした、お疲れさまでした。
☆2005年2月20日(日)午前10時から
今年(2005年)に入って初めての活動でした。
天気も良く、子どもたちが参加してくれて15人ほどで
雑木林の下枝刈りとログハウスづくりを行いました。
下枝刈りは全てはできませんでしたが、
林がかなりすっきりしてきました。
次回もう少しやれば、もっとすっきりするでしょう。
また、ログハウスは、屋根ができたせいで、
風の影響をかなり受けるらしく、少し傾いたので
それを補正し、筋交いやロープで補強しました。
早く壁を入れないといけませんね。
☆2005年3月12日(土)午前10時から
この日は、前日の雨も上がり、多くの子どもたちも参加してくれ
30名近くが集まりました。
みんなで、ナタやノコギリを使い、雑木林の下枝を刈り、
刈った枝の片付けを行いました。
刈った後は林がすっきりし、子どもたちは林の中に入り、
まだ小さな木ですが、木に登ったりすることが
できるまでに林が成長しました。
一方、ログハウスのほうも壁材の落としこみが進み、
次回以降は窓を付けるところまで行けそうです。
また、今年はたくさんのシイタケができ、
みんなで分けました。
今後の活動日を4月23日(土)と5月8日(日)に決めました。
皆さんぜひ見に来てください。
☆2005年4月23日(土)午前10時から
今日は、人数も7~8名程度と少ないが、ログハウスの壁づくりを行った。
2月から3月にかけて無駄な枝をのぞいた広葉樹の木々が芽生えてきて、明るい森を作っていた。
今年の夏は暑い下草刈りの合間には、広葉樹の日陰で、休みをとれそう。
昼には、野草の天ぷらを作った。何年か前にほだ木を作った椎茸もたくさんとれて、みんなで分けて帰った。
☆2005年5月8日(日)午前10時から
ゴールデンウィークも最後の日曜日。天気は曇り、体を動かさないと少々肌寒いかなという一日でした。
大人8名、子ども6名の14名が集まった。
午前中は、下草がだいぶ伸びてきたので、草刈り機や手鎌で、雑木林の半分ぐらいと道の下草刈りをした。
また、作業がしやすいように、ログハウスの周りの草を刈った。
子どもたちはたけのこ堀をしたり、焚き火をしたり。
昼は、燻製を作ったり、タンポポの花や野草のてんぷらを作ってみんなで食べた。
午後はログハウスの壁づくり。丸太をチェーンソーで壁材用の寸法に切っていった。
丸太は数年雨ざらしの状態だったので、中には腐っているものもあったが何とか必要な本数は確保できた。
残りの時間で、壁の柱の溝にはめ込むために、切った丸太の両端を削る作業や鉋をかける作業を行って16時ごろに終了した。
次回は通常通り第2日曜日である6月12日(日)。雑木林の下草刈りとログハウスの壁づくりです。
☆2005年6月12日(日)午前10時から
今日は比較的過ごしやすい気温のなか、10人程でログハウスの壁積みを行った。
少しずつではあるが、だんだん高いところまで積み上がってくる。
午後ちょっと早めに終了にしたが、もうそろそろ、窓を取り付けることになりそう。
最後に、先日届いた移動式製材機をみんなで見た。今後はこの機械が威力を発揮しそうだ。
☆2005年7月3日(日)午前10時から
今日は下草刈りとログハウスの壁材づくりと窓枠の設置を行った。
夏になると草が伸びるのが本当に早いし、雑木林全体の成長がよくわかる。
次回は9月になってしまったが、草刈りが大変だろう。
☆2005年9月11日(日)午前10時から
今日も暑く、ログハウスの窓枠の設置及び雑木林の草刈りを行った。
今回は、この雑木林に学校の生徒を連れてきたいという先生が下見にきました。
また、横浜市の方の参加もありました。
次回は、ログハウスの窓の設置及び床用の束の設置などで10月2日に行います。
☆2005年10月2日(日)午前10時から
参加者は子どもたちも含め、11人。
下草刈りを少し。
ログハウスの床束を設置し、また、子どもたちも参加して
ログハウスの壁材づくりを行いました。
雑木林では、とても山栗とは思えない大きな栗がたくさん取れました。
次回は大引きの設置から床板張りまでやってしまい、
12月にはログハウスの中で忘年会ができるといいなぁと
半分本気(ほとんど本気?)、半分期待で16時前には解散しました。
☆2005年11月13日(日)午前10時から
参加者は子どもたちも含め、11人。
子どもたちも参加して、大引きの設置から
ついに床板張りまでやってしまいました。
囲炉裏用に真ん中を空けました。
また、壁も少しばかり積みました。
子どもたちは焚き火をして、落花生を煎ったり焼き芋を作りました。
次回12月は、ログハウスの壁組等を行った後、一人1品持ち込みで、
バーベキューコンロで、適当に焼いてお疲れさん会をやろうということになりました。
☆2005年12月4日(日)午前10時から
雨で予定していた作業は中止し、床を張ったログハウスで忘年会をしました。
壁が途中なので、少々寒かった(かなり?)のですが、外でやるより格段に快適でした。
10人以上は十分に入れる広さは確保したといった感じです。
来年は待ちに待ったログハウスの完成といきますか?
☆2006年2月19日(日)午前10時から
曇りがちで少し寒い日でしたが12人が集まりました。
午前中は、皆で雑木林の手入れ。
葉がついたときにも容易に林の中に入れるように下枝を払ったり、
木が成長するよう木と木の間隔を広げるため、木を間引いたりした。
種や苗木から育ててきたので、木を切ってしまうのが躊躇された。
刈った木や枝を片付けると、雑木林全体がすっきりした。
昼食をとって、午後からは、ログハウスの壁づくりと窓のはめ込みを行った。
今年中には念願のログハウスが完成するだろう。
☆2006年4月16日(日)午前10時から
朝、家を出るときは降っていなかったが、現地に着くと雨が降り出した。
参加者が心配だったが、それでも9人が集まった。
雨よけとして、ログハウスの入り口予定の前面にビニールシートを張って作業開始。
足場の材木と支柱の撤去作業と、ログハウスの中で、壁と窓付けの作業。
雨がやまないので、作業は午前中で終了。昼食をとって解散となった。
先月は雨で中止、今月は雨で午前中のみの作業。
なんだか、今年は雨にたたられている?
ログハウスの今年中の完成に暗雲か?
ここ数か月、雨にたたられ、活動ができなかったのですが、今日(7月9日)もまた雨が心配されましたが、
なんとか下草刈を行うことができました。
参加者は大人5名と子ども1名。それに、山武市の社会福祉協議会の方が4名。
7月26日に当会の雑木林を使い、また当会代表の清水さんが講師となって「夏休みボランティア体験教室」(社会福祉協議会主催)を実施する予定なので、その下見を兼ねて参加されました。
人数が少なかったのと、午後から用事のある人が多かったので、午前中限定で、下草刈をしました。
草刈り機2台とあとは手ガマでしたが、全体の3分の1くらいはできたのではないでしょうか。
それから、ミヤマクワガタを2匹(オス)捕まえました。(後で林に離しましたが)。
昨年くらいから、カブトムシやクワガタが見られるようになりました。
これも、雑木林が形になりつつある証拠でしょうか。
今後の日程について相談した結果、これからは活動日を固定して
毎月第二日曜日とすることにしました。
次回ですが、8月はお盆と重なるので中止とし、9月10日(日)になります。
9月は下草刈とログハウスづくりです。
2か月ぶりの活動でしたが、参加者は5名とわずか。
その上、この日は久しぶりに非常に暑い1日でした。
そんな中でも、少人数で頑張って、ログハウスにバルコニーがつきました。
参加者の皆さんご苦労様でした。感謝!感謝!
朝から雲ひとつない快晴でしたが、台風から変わった低気圧が北海道沖にあって風が強い一日でした。
参加者は子ども2人を含め9名と先月よりは多かった。
作業は、下草刈り、冬に間伐する木の選定(黄色いビニール紐を巻きつけました)。
そして、前回仮設置したバルコニーづくり、窓づくり。
バルコニーは次回には完成するでしょう。
なかなか壁が進みませんが、今回のような風の強い日にログハウスの中で食事ができるのは助かります。
これからは、日没が早くなり、作業時間が短くなりますが、その分を参加者の数でカバーしたいと思っています。
皆さんよろしくね。
日差しは強かったですが、風もあり、じっとしていると寒いかなという天気でした。
参加者は新しい方が1家族3名を含め12人。
作業は、バルコニーづくり、壁組み、窓枠づくりでした。
作業は順調に進み、バルコニーはほぼ完成し、壁もかなり積み上がりました。
次回は今年最後の活動になります。壁組みと窓の設置を予定しています。
雑木林のほうも、もう1、2年すれば、育った木でシイタケの原木がつくれるでしょう。
壁が積みあがり、窓が入れば、少しくらい寒くても、お昼は暖かい(?)ログハウスの中で食事ができます。
つくり始めて数年が経過しますが、来年にはログハウスを完成させたいですね。
今年最後の作業ができるか心配でしたが、前日までの雨も上がり、参加者は9人。
皆さん忙しいのか、少し寂しい人数でした。
作業は、バルコニーの壁組み、窓枠の補強でした。
工期が長くなってしまい、柱など補強が必要なところもありますが、
写真を見てもらえれば分かるように、あともう少しです。
来年には完成しそうでしょう。
皆さん、来年はぜひ時間を見つけて参加して、完成を皆で祝いましょう。
新年初めての活動日でしたが、参加者は4名。
正月早々だから、皆さん忙しいのでしょうか。
ログハウスづくりも最終段階、でも、先行きがちょっぴり不安です。
少人数でしたが、作業は順調に進み、壁もかなり積みあがりました。
壁材が残り少なくなってきたので、杉の木を玉切って壁材用の丸太を用意しました。
次回は沢山の人が参加してくれますように。
1月の参加者は4人で今年はどうなるかと心配でしたが、
今日は子どもたち6名、久しぶりの参加者も含めて総勢15名。
風が強かったけれど、日差しは暖かく、久しぶりに元気な声が響きました。
作業は、雑木林の間伐、ログハウスの壁組み、入り口の窓枠作成でした。
間伐と枝払いで雑木林もすっきりしてきました。
子どもたちは名札をつけた自分の木の太さを測って、成長を確かめていました。
壁ももう少しで完成です。
竹炭づくりやシイタケづくりにまた取組もうかとの話もしました。
なお、1月20日に韓国の森づくりNPOが私たちの雑木林を見学に見えました。
韓国(社)生命の森のマウルスプ委員会です。
民間が主体となって保存・管理している森を見学して、韓国におけるこれからのマウルスプ(伝統の森)の運動方向を提案していくため、来日したそうです。
佐倉や四街道、柏も見学するそうです。
当会では代表の清水さんが説明し、案内しました。
今回の参加者は子ども1人を含め5人でした。
毎月第2の日曜日ということにしていたのですが、3月が雨で中止になり
ホープページに4月のお知らせを掲載しなかったからでしょうか。
雑木林の木々に芽吹きが見られました。シイタケも少し採れました。
作業は、壁材用の丸太の皮むき、壁材づくり、できた壁材のはめ込み、窓枠づくりでした。
大人4人にしては、かなり進んだ?かな。
ログハウスづくりが長引いていますが、いつまでも完成を先送りにしていてはいけないということで
多くの人に声をかけ作業に参加してもらい、7月までの3回で完成させ、
8月には完成パーティーをやろうということに決めました。
次回以降は8月のパーティに向けて少々の雨でもやります。
4月には葉はほとんどついていなかった木々ですが、
この1か月で葉が茂り、まさに新緑の季節です。
参加者は7人。子どもが1人と女性が4人、男性は2人だけ。
それでも、壁材用の丸太の皮むき、壁材づくり・落とし込み、窓枠・入り口枠づくりと
少数精鋭で写真のとおりかなり進むことができました。
みんな、木屑を体中に浴びながら頑張りました。
8月の完成披露まで、後2回ですが、多くの方が作業に参加してくれると何とかなりそうです。
(6月10日)
雨が心配な曇り空の中、8人が集まりました。少しくらいの雨なら作業をやることにしていましたが、
作業を開始しようとしたら、とたんに雨が降り始め、直にやむだろうとログハウスの中に避難。
雨の日ほど、まだ完成はしていませんがログハウスのありがたみがわかります。
雨はやむどころか、豪雨になり雷まで轟きわたる天気になってしまいました。
少しでも作業を進めないと8月の完成披露ができなくなるということで、
午後には天気も回復するだろうと早めのお昼を食べて待ちました。
昼過ぎに雨がやんだので、残りの壁づくり、入り口脇の窓枠づくりをする一方で、
ログハウス内の床貼り作業を行いました。
床に使った材もこの雑木林をつくる時に伐採した杉の木からつくったものです。
床貼りも無事完了し、17時近くに作業を終了しました。
(6月17日)
8月に間に合わせるため、先週に引き続き、集まれる人(4人)で作業。
残っていた上部の壁を入れ、外壁と内壁に防腐剤を塗りました。
また、入り口脇の窓づくりも並行して続けました。
忘れてはいけない雑木林の下草刈もしました。
柱が少し傾いている(?)せいで、窓づくりはかなり難航しています。すべて現場合わせです。
残っている入り口ドアの作成、入り口脇の窓の取り付けは次回にすることとして
16時過ぎには今日の作業を終えました。
隙間だらけ(?)ですが、冬ではないので、次回作業をすれば、
何とか8月の完成披露(8月18日(土)、19日(日)の予定)が迎えられそうです。
梅雨時の晴れ間の中、久しぶりに14人が参加。
ログハウスの外壁上部の取り付け、正面窓、出入り口のドアの作成・取り付け。
雑木林の下草刈と順調に作業は進みました。
途中、差し入れのスイカを食べながら、参加者皆で、完成を目の前にして悔しくも亡くなられた「おんじ」のために8月に完成披露をしようと頑張りました。
無事に写真のように一応完成させることができました。
(代表から)
山武のログハウスづくりに参加いただいた皆様
本日の集まりで、ドアも取り付けることができ、思えば平成13年の杉の皮むきから
6年あまりかかったログハウスも完成となりました。
本日までいろいろお手伝いいただいた方、ほんとうにありがとうございました。
来月の18,19日は思いっきりビールを飲みましょう。
それと同時に、せっかく皆様に作っていただいたこのハウスを今後、皆様にできるだけ使っていただきたいと思っています。
そして、ずっと来ていただいていたKさんが亡くなって後に完成したのも何かのご縁だと思います。今日は、とてもお忙しい中、Kさんの奥さんもご挨拶にきていただきました。
人のつながりはとても不思議だと思います。
何かを後に続く人に受け渡せればと思います。
合掌。
ログハウスの完成披露の日です。
ここのところ猛暑が続いていましたが、今日は少しばかり過ごしやすい曇り空。
午後から、三々五々集まり、土器を焼く者、周辺を散策する者、買出しに行く者と
皆それぞれ、夕暮れからの完成パーティーを待ちました。
暗くなってきたころ、パーティーが始まり、ビールやお酒を片手に、これまでの活動の
写真をパワーポイントでまとめて、ログハウスの縁側に立てたスクリーンに映し出し
スライドショーを鑑賞しました。懐かしい写真が沢山でてきました。
また、会員のバイオリンの演奏を楽しみました。
1998年10月に活動をスタートさせて9年。いろいろなことがありました。
メンバーも何人かは変わり、初めのころから関わった者は成長し、また歳もとりました。
代表の清水さんの次男はまだ生まれていなかったのが、もう小学2年生になりました。
影も形もなかったログハウスが完成し、雑木林も少しずつ成長しています。
これからも、このログハウスを拠点に、いろいろな活動をしながら、
雑木林の成長を皆で見守っていきたいと思います。
12月9日は、雑木林で間伐を行い、ひととおり終わりました。
雑木林の木々も大きくなり、来年の葉が広がって行く頃には、子供たちに木の名前を当ててもらい、
それを木のプレートに木の名を書いてつるしては、など、いろいろアイデアが出ました。
参加者は5人ほどで、のんびりやりました。(写真をとるのを忘れてしまいました。)
今回参加された人で、1月に八街に引っ越してくる人がいて、新居で薪ストーブを設置するので、
薪を新年早々に取りに来たいという人がいて、その人のための薪(主に小枝)もつくりました。
2008年子年の最初の活動日でした。天気にも恵まれて11人(最後は15人)が集まりました。
今日の作業は、前回間伐したコナラやクヌギ、サクラの原木を利用したほだ木づくり。
ドリルで原木に穴をあけ、シイタケやヒラタケ、ナメコの種駒を木槌で打ち込む作業。
それと並行しながら、サクラのチップを使って、さつま揚げやチーズ、はんぺんなどの燻製づくりもしました。
お昼にそれらをみんなで食べて、午後は隣の杉林の中にほだ木の仮伏せ作業をしました。
次回は、雑木林の間伐とログハウスの屋根下の壁づくり、そしてお昼はログハウスの中で
おでんを食べようということになりました。おでんの具はみんなで持ち寄ることにしました。
☆2008年3月9日(日)午前10時から
昨日は、お天気もよく暖かかったのですが、総勢5名とちょっと寂しかったですが、前回間伐して搬出し切れなかった間伐木を搬出したり、椎茸菌をうったりしました。(写真は撮るのを忘れました)
もう、桜の木(染井吉野ではないかという話)には花芽とおぼしきものがついており、春の訪れを感じました。
雑木林も大きくなってきて手もかからなくなりましたので、これからは雑木林を楽しむイベントなどをやってみようという話になりました。
☆2008年6月8日(日)午前10時から
あいにくの雨模様の天候でしたが、大人8人、子ども6人の14人の参加でした。
木々も生長し、葉も生い茂り、前回3月の裸木の頃とは大きく違っていました。
午前中、大人たちは、草刈り機3台と草刈カマを使っての下草刈り、子どもたちは簡易トイレづくりをしました。
蒸し暑く小雨が降る中、みんな汗を拭きながら、がんばりました。
お昼を食べて、午後も作業続行。おかげで下草刈もひととおり終えることができました。
また、子どもたちは、木の名札付けをしました。9種類の名札をつけましたが、まだ名前の分からない木がたくさんあります。
この雑木林にはいったい何種類の木が生えているのでしょうか。
ちなみに、帰って調べたら、次の23種類を植えた(種をまいた)ことになっていました。
カエデ、ムクロジ、ゴンズイ、クマシデ、コブシ、エノキ、ムクノキ、クヌギ、ホウノキ、ヤマコウバシ、エゴノキ、コナラ、コナラ、イヌシデ、シイ、ケヤキ、ヤマグリ、イイギリ、アオハダ、ヤマザクラ、センダン、モチノキ、モミジ
このほかにも、鳥や小動物が種を運んできて発芽した木もあるようです。
雨模様だったので、いつもより早く15時には終了しました。
☆2008年7月13日(日)午前10時から
今日は大人と子ども合わせて10人の参加でした。
午前中はみんなで刈払い機や柄の長い草刈カマを使っての下草刈。斜面の下のほうは結構笹が侵入していました。
午後は、草刈と、女性トイレの設定(集まった当日にまわりに布をはれるようにねじ等をうちました)、ログハウスの屋根の下の三角形のところに窓を入れるため、そこにわたしてあった材木の整理などをしました。
最後にお昼過ぎにセッティングしてあった燻製をみんなで食べて、3時過ぎに終了しました。次回は、9月の第二日曜日にしました。
昼食は木陰で涼しくとりましたが、最近の食生活の変化の話しとか、ゆっくりとした時間がすごせました。なにか、あの雑木林を使ったいい催しなどができればいいと思います。
☆2008年9月14日(日)午前10時から
今日は大人と子ども合わせて13人の参加でした。
8月の作業がなかったので、2か月の間に笹や雑草が生い茂り、ログハウスの前はごらんのとおりの有様(左の写真)でした。午前中はみんなで刈払い機や柄の長い草刈カマを使って、雑木林の中の下草刈やログハウスの前の雑草の取り払い作業をしました。蒸し暑かったのでかなり汗もかきましたが、ログハウスの前も上の右の写真のようにきれいになりました。また、雑木林の中もすっきりしました。
お昼は、大人たちは雑木林の中の木陰で、今後の話をしながらお弁当を食べました。
子どもたちはログハウスの中でお弁当を食べていました。日差しがあって暑い日は本当に日陰がありがたいです。木のありがたさが身に沁みます。
午後は、草刈と、子どもたちは簡易ツリーハウスづくりの準備をしました。うまくできるでしょうか。これからが楽しみです。
☆2008年10月12日(日)午前10時から
今日は大人と子ども合わせて19人と久しぶりに多くの参加者がありました。
午前中はみんなで間伐作業。太い木はチェーンソーで伐採し、細い木は子どもたちが鋸を使って刈りました。刈った木や枝葉を林の中から集めてきて、軽トラックに積み、運び出しました。人数も多かったので作業は順調に進み、お昼近くには雑木林の中もすっきりしました。
お昼には、3時間近くかけてつくった鳥のささみの燻製を食べました。
午後は、子どもたちを中心に簡易ツリーハウスづくり。また簡易トイレづくりをしました。その途中で、溝腐れしている30年を越えた杉の木を2本切り倒しましたが、みんな伐採を間近で見るのは初めてらしく、興味深げで見ていました。
今年の春に植菌したナメコとヒラタケが少しですが、もう出ていました。来年の秋には沢山収穫できるといいのですが。
☆2008年11月9日(日)午前10時から
今回は、二酸化炭素吸収量を測定するための調査方法の相談とツリーハウスの補助支柱用のスギ丸太の皮むき、仮設トイレの設置をしました。
次回は1月18日で、予定する作業は次のとおりです。
1 現在の雑木林の二酸化炭素固定量の測定をしようということで、2ヶ所ほどエリアを決めて樹高と胸高直径を測って、平均の樹高と胸高直径を求めます。この測定と同時に、雑木林の立木本数をすべて数えます。両者を乗ずれば、雑木林の炭素量が推定できます。
来年の秋以降(一成長期経過後)に同じ調査を行い、炭素量を推定します。後者から前者を減ずると、来年成長期間に固定した炭素量を推定できます。ということで、雑木林の本数、高さ(樹高)、太さ(胸高直径)の計測作業を行います。
2 ツリーハウス作り(補助支柱用のスギ丸太の設置(立て込み)ほか)
☆2009年1月18日(日)午前10時から
今回は、子どもたち5人を含めて14人の参加でした。
雑木林の二酸化炭素吸収量を測定するための調査として、雑木林の本数、高さ(樹高)、太さ(胸高直径)の計測作業を行いました。
雑木林には400本以上の木が生えており、そのうち250本余りの高さ(樹高)、太さ(胸高直径)を計測しました。高いもので13メートル余りに生育していました。
詳細は後ほど掲載します。
次回はツリーハウス作り(補助支柱用のスギ丸太の設置(立て込み)ほか)を行います。
☆2009年2月8日(日)午前10時から
ちょっと風が強く寒かったですが、天気もよかったので、みんなでツリーハウス作りをしました。
ツリーハウスの基礎柱を立てて、上に板を張っていくための根太も何本か設置しました。
来月の活動日(3月8日)にはツリーハウスの床板もはれそうで、何人か上に乗れそうです。
また、進化し続けている燻製(今回はスペアリブ)は大変好評でした。
次回は、ベーコンに挑戦です。
☆2009年3月8日(日)午前10時から
今回は参加者が少なかったですが、大人と子どもの計10名程度で、ツリーハウスづくりをしました。
お昼から雨になったので午前中で切り上げました。
ツリーハウスは根太をもう少し取り付けて、下の柱に筋交いを入れて終わりました。
4月、5月も第二日曜日にやるということになりました。
☆2009年4月12日(日)午前10時から
作業は、ツリーハウスの根太、大引きの設置、床張りでした。
そのほか、ログハウスからツリーハウスにむかってロープを張り、ロープをくぐらした円筒に吊り下げたトラロープを持って滑って行けるような仕組みを作り、遊びました。
☆2009年5月10日(日)午前10時から
快晴の中、子ども4人を含めて12人の参加で下草刈とツリーハウス作りなどを行いました。
先月はまだ枝ばかりが目立っていましたが、木々はあっという間に若葉をつけていました。新緑の季節です。
午前は刈払い機や柄の長い下草刈用の手鎌を使って下草を刈りました。子どもたちには柄の長い鎌の扱いは難しそうでした。
その後、ログハウスの前に積んであった腐りかけた丸太などを片付けました。
材を除くと、シマヘビ、山カカシ、アオダイショウがかたまって出てきました。(びっくり)
お昼を日陰で食べて、午後は子どもたちも参加してツリーハウスの床張り。これで安心して上がれます。
さらに、昨年仮伏せして忘れてしまっていたシイタケのほだ木の本伏せをしました。
雑菌が入っていなければいいのですが。秋に収穫が出来ますように祈るだけです。
☆2009年6月14日(日)、7月12日(日)午前10時から
6月14日
梅雨の合間の一日に10人ほどで下草刈とツリーハウス作りなどを行いました。
午前は刈払い機や手鎌を使って下草を刈りをするグループと、ツリーハウスに上がるはしご作りをするグループに分かれて作業をしました。
午前中で草刈もはしご作りも終えて、お昼を食べながら、間伐材を使った家具作りについて話し合いました。参加者の中に家具作り職人の方がいるので、試作品を作って(考えて)みようかという話になりました。
午後は作ったはしごを試してみましたが、大人には足を掛けるところが少し浅い?かもしれません。
滑らないように慎重に試しに上ってみました。
7月12日
ログハウスの周りをざっと草刈して、脇の桧の枝が畑側に伸びてきていたので、木にはしごをかけて、切り落としたりしました。
もう、雑木も大きくなり、通路も上部が葉に覆われて、草があまり生えてこなくなったので、正直驚きました。
皆午後から予定があったりしたので、お昼を食べて切り上げました。
次回は8月は休会にして、9月の第二日曜日に東京農業大学の上原先生を招いてのセミナー「木の二酸化炭素吸収機能と癒しの機能について」(主催:地域の木を使おうかい)を実施する予定です。
午前中に先生によるセミナー(山武の森文化ホール等をかりて、パワーポイントによる説明など。場所は今週中に決定)
午後は雑木林に移動して、現地での話しといったことを予定しています。
場所、時間割は今週中に決める予定です。
☆2009年9月13日(日)午前10時から
今回は、千葉県の地域活性化プラットフォーム事業に参加している団体「地域の木を使おうかい」が主催した森林の癒し効果に関するセミナーに協力しました。
午前中は、さんぶの森文化ホールで東京農業大学の上原先生が「森林を健康に 人も健康に -千葉県山武市における森林療法の可能性を考える-」と題して、講演を行いました。
森林の癒し効果について、沢山の事例をもとにお話いただきました。
主催者側のスタッフも含めて、地元山武市内をはじめ都内や館山からも、森林や森林療法に関心のある100名あまりの参加がありました。
午後は間伐コースと、雑木林(当会の活動地)と杉林の散策コースにそれぞれ20名あまりが参加して、森林の癒し効果を体験しました。
この協力を通して、当会の活動場所に散策路を設けようという話があがり、来月から整備していくことになりました。
☆2009年10月11日(日)午前10時から
今回の参加者は10名。散策路の整備(下草刈など)を行いました。雑木林~杉林~大杉~杉林~雑木林と一周できるように整備しました。ゆっくり歩いて30分くらいでしょうか。途中に伐採した丸太でベンチなどを作ろうと、写真にはありませんが、一つ試しに作ってみました。今後、所々にベンチを置くなど散策路、癒しの森として整備していく予定です。
午後には30メートルほどある倒れ掛かった杉の木を切り倒しました。散策路脇にそのまま放置して、その長さを実感してもらうことにしました。
☆2009年12月13日(日)午前10時から
今回の参加者は20名。恒例?の会の忘年会です。少々寒かったけれど、ログハウス前でバーベキューをしながら、馬頭琴の演奏、子どもたちによる歌やコントの披露、ギター伴奏付デュエットなど、楽しいひと時を過ごしました。
雑木林をつくる会の活動も10年が経ちます。種子や苗木から育てた木々も大きくなりました。
これからも、子どもたちの(、大人たちも)元気な声が聞こえる素敵な雑木林にしていきたいと思います。
|